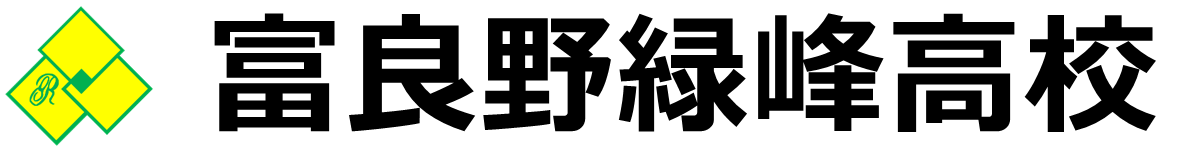電気システム科
「ものづくり」をキーワードに堅実な職業人の育成と電気の技術・知識を学びます。

基礎的・基本的な学習

電気の勉強には基礎的な数学が必要で、本校でも多くの時間学びます。皆さんにもしっかりと学んできてほしいので、春休み期間中に数学の復習課題も用意されています。また、電気実習にはレポートがあり、口頭試問を含み提出をすることで理解力をつけていきます。
国家試験

第二種電気工事士を中心に国家資格の取得を推進しています。第二種電気工事士は2年生で全員受験し、第一種電気工事士は2・3年生の希望受験で取得を目指し、そのほかの資格についても希望に応じて取得をサポートします。
様々な体験学習

地域の会社や道内の工場などを見学し見識を広めます。また、様々なコンテストへの出場や、工業系大学の講義を受ける授業もあります。
取得できる資格
- 第三種主任技術者
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
- 二級電気工事施工管理技士
- 危険物取扱者 各類
- 工事担任者
- 二級ボイラー技士講習
- 二級ボイラー技士試験
- 第二級陸上特殊無線技士
- 計算技術検定
- 情報技術検定
- リスニング英語検定
- パソコン利用技術検定
電気システム科の専門科目
工業の各分野における基礎科目
- 工業技術基礎
- 工業技術の基礎を身につけ、実際に実習器具を使用して、電気現象の観察、電圧・電流などの測定をしたり、パソコンの操作や制御・電気工作・工事等を通して体験的に電気を理解します。
1.人と技術と環境
2.基礎的な加工技術
3.基礎的な生産技術 - 実習
- 工業の各専門分野に関する技術を実際の作業を通して総合的に学びます。
1.要素実習
2.総合実習
3.先端的技術に対応した実習 - 課題研究
- 各自でテーマを決め、調査・制作を行います。
1.作品製作
2.調査研究実験
3.産業現場等における実習
4.職業資格の取得 - 製図
- 電気機器の製作図や設計、電気設備の配線・接続図を描きます。CADについても学びます。
1.製図の基礎
2.各専門分野の製図・設計製図
3.CADの基礎 - 工業数理基礎
- 具体的な事柄を数理的に、実際的に処理する基礎的な方法を学びます。
1.工業の事象と数式
2.基礎的な数理処理
3.応用的な数理処理
4.コンピュータによる数理処理 - 情報技術基礎
- コンピュータの役割を理解し、ハードウェア・ソフトウェアに関する基礎的な知識と技術を学びます。
1.産業社会と情報技術
2.コンピュータの基礎
3.コンピュータシステム
4.プログラミングの基礎
5.コンピュータ制御の基礎
6.情報技術の活用
電気システム科の専門科目
工業の各分野に関する科目
- 電気基礎
- 直流回路・静電気・磁気・交流回路などの性質や諸量の計算方法について学びます。
1.直流回路
2.磁気と静電気
3.交流回路
4.電気計測
5.各種の波形 - 電気機器
- モーターや発電機・変圧器などの電気機械について学びます。
1.直流機器
2.交流機器
3.電気材料
4.パワーエレクトロニクス - 電力技術
- 発電・送電・配電について学習し、照明や電熱・化学工業・電気鉄道などの仕組みや利用について学びます。
1.発電
2.送電と配電
3.自動制御
4.省エネルギー技術
5.各種の電力応用
6.電気に関する法規 - 電子技術
- トランジスタやIC・コンピュータの仕組みについて学びます。
1.電子技術の概要
2.半導体と電子回路
3.AD変換とDA変換の基礎
4.通信システムの基礎
5.音響・映像機器の基礎
6.電子計測の基礎 - 電子計測制御
- コンピュータを使った電子制御の方法について、基礎的な知識・技能・技術を学びます。
1.電子計測制御の概要
2.シーケンス制御
3.フィードバック制御
4.コンピュータによる制御の基礎
令和5年(2023年)度学年別教育課程表
学年別教育課程表(pdf 106KB)
高い就職率と低い離職率
工業科出身の生徒は、機械の操作や製図の作成などの基本技術をある程度、習得しているので、就職や大学進学後、実験や実習で他の学生をリードできると、高い評価をいただいています。 また、高卒就職者の約半分が3年以内に離職しているのに対し、工業科卒業生の離職率は、10人に1人程度です。 ものづくりの仕事に必要な専門知識と技術を学んでいることで、就職前から会社の仕事のイメージができ、就職後も、比較的不安を感じることなく仕事に打ち込める学科です。
授業スナップ